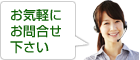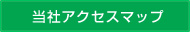相続対策と相続税対策について(その1)
2025.2.1
今回から相続対策と相続税対策についてお話しして参ります。
第1 相続対策(遺言の作成)について
-
1 「相続対策」は、「相続税対策に繋がる」と言われ、更に相続税の軽減対策や納税資金対策にも繋がるので「100人中100人に必要だ」とも言われています。
- (1) さて、元・作家、経済評論家、株式投資の名人で「金儲けの神様」と呼ばれた亡邱永漢さんが、その著作『相続対策できましたか』(PHP研究所)を物しています。
- (ア) その「第一章 死んだら財産争いが始まります」で、「相続は人生最後の宿題です」とし、「第二章 相続対策は十年の歳月をかけて」と題しておりますが、結局「人生最後の宿題」は「遺言書」の作成に帰着します。
- (イ) 今年はそれを「人生早目の宿題」として考えて見ましょう。既に「遺言書」を作られた方には暫しお付き合い願います。
- (2) 邱さんの言う「死んだら財産争いが始まります」は他人事ではありません。
- (ア) 親の「うちの家族に限って揉める訳がない」、「揉めるほどの財産はないし、子供達は生活に困っていないので大丈夫だ」との声はその願望に過ぎません。子供達の仲は、親の欲目と、子供達同士が受け止めている感覚とは異なることが多いのです。
- (イ) 子(兄弟姉妹)が仲良くても親が亡くなりその重石がなくなると、親の介護や生前贈与などを巡る不満の鬱積、各家庭の事情(子供の教育費・自宅の住宅ローンなど)もあって、金銭的な利害が対立し、話し合いは縺れて感情的争いになり、家族関係が絶縁する例があります。「遺産は家庭争議の元」になりかねません。
- (3) 「生前に財産の分け方を家族で話し合って遺産分割する」との考え方もあり、親の威光でその家庭教育が浸透している場合は兎も角も、生前の遺産分けの約束には法的拘束力がないし、これが却って親の生前に「争続」問題を生じさせる結果となることもあります。情けない話ですが「お金を見て目が眩まない人はいません」。
- (4) 決して望ましくないが、『きょうだいは他人の始まり』を肝に銘ずべきです。
- (1) さて、元・作家、経済評論家、株式投資の名人で「金儲けの神様」と呼ばれた亡邱永漢さんが、その著作『相続対策できましたか』(PHP研究所)を物しています。
- 2 ところで「相続」とは、財産上の地位(又は権利義務)と「法律上の地位」の承継であり、非財産法(身分法)上の地位は承継の対象に含まれません。
- (1) 相続は、死亡者(被相続人)の「最終意思」か「法律の規定」に従います。
- (2) 「法定相続」は被相続人の意思にかかわらず、法律の規定に基づいて効力が発生するもので「無遺言相続」とも呼ばれます。
- (3) これに対し、「遺言による相続」は、遺言者(被相続人)の財産的地位(又は権利義務)の承継が、遺言者の「最終意思」に基づいて行われるのです。
- (ア) 「遺言」には「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」もありますが、一番安全な「公正証書遺言」に限ると言って差し支えないと思います。
- a) 「遺言公正証書」は、法務省が任命した公証人が遺言者の意思を確認して作成するので、その効力に争う余地はありません。
- b) 例え相続人が一人であっても、遺言書には相続の執行手続(預貯金の解約手続など)を簡易化できるメリットがあるので、それを活用すべきです。
- (イ) 但し「遺留分」のある一定の相続人がいる場合は、遺言は遺産の一定割合で法律上の制限(法律による相続)による修正を受けることがあります。
- (ウ) 遺言は、財産法上の地位の承継のみを内容とするものですが、身分法上の地位ないし権利義務の変動を目的とすることもあります。
- (ア) 「遺言」には「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」もありますが、一番安全な「公正証書遺言」に限ると言って差し支えないと思います。
-
3 通常「相続人」と呼ばれる「法定相続人」は<配偶者の株>と<血族関係の株>があり、配偶者が先に死亡すると<配偶者の株>は<血族関係の株>に吸収されます。
-
(1) <血族関係の株>は、第1順位は子(人数で分ける)、代襲相続人(孫の相続)、再代襲者(被代襲者の直系卑属、民887Ⅲ)、養子、胎児(民886)ですが、<子が相続放棄した場合>その子(孫)達は相続人になれないので注意を要します。
-
(2) 第2順位は直系尊属(代襲相続はない)、第3順位は兄弟姉妹(その子(甥・姪)に代襲相続権があり、再代襲は無い)で、兄弟姉妹には遺留分権はありません。
-
- 4 「相続対策」で最優先すべきは「相続争いの防止」で、「納税資金対策」も必要です。
- (1) 財産を残したい人、例えば家族の中の弱者、遺言者の介護に当たってくれた嫁などがいれば、確実に財産を残せるように生前対策として遺言書の作成は必至であり、これにより家族の幸せを確保するのが重要です。その結果として「節税対策」にも役立つ取り組み方が望ましいと思います。
- (2) 被相続人の判断能力が低下する前に、先ず「遺言公正証書」を作成し、更に「任意後見契約公正証書」を締結し、相続対策もできるようにしておくことも大事です。
- (ア) 被相続人が成年後見人を決めて、財産管理やその処分権限を具体的に与えておけば、被相続人の判断能力が低下あるいは喪失しても相続対策は可能です。
- (イ) 成年後見制度には「任意後見契約」と「法定後見制度」があり、「法定後見」は被後見人の財産を守ることが任務となり、財産の贈与や自宅売却には家庭裁判所の許可を要し、その実現は極めて困難と言えます(次回説明します)。
- (3) 「相続対策は先ず財産の棚卸しから」で、先ず相続財産の全部を把握し、相続人への財産の配分を考え、「遺言書」の案を構想し、相続税の負担がある場合は「納税資金」についても考えておくことが大事です。
- (ア) 遺言書に相続財産の全容が明確に記載されてあれば、遺言の執行手続が速やかにでき、遺産分割を早期に終えることができます。
- (イ) 夫婦に子供がいなく、妻又は夫に遺産全部を相続させる場合は、親あるいは兄弟姉妹も法定相続人となるので、遺言書を作成しておくことが最も大事です。
- a) 遺言書がないため、妻が夫の姉妹から遺産分割を求められ、夫婦が居住したマンションを売却せざるを得なかった事例もあります。
- b) これは「法律が冷たい」のではなく、夫婦が相続対策を怠っていたのです。
- (ウ) 司法統計によると遺産分割調停(家庭裁判所申立事件)は年々件数が増加し、令和4年は14,371件に達し、その8~9割が相続税がかからないか、殆どかからない場合が占めており、「第一章」の「死んだら財産争いが始まります」を地で行っているかのようです。
筆者紹介

特別顧問
弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人
- 経 歴
- 宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」