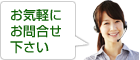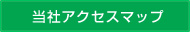相続対策と相続税対策について(その2)
2025.3.1
前回に続いて、相続対策(遺言の作成)についてお話しします。
第2 相続対策(遺言の作成)について
- 5 相続財産の分割の方法として<「遺言の作成」>について話します。ご存じの通り、遺言がない場合は法定相続人全員の「遺産分割協議」により、合意に至らない場合は「法定相続」によることになります。
- (1) 共同相続人のうちの特定の相続人に遺産を取得させる場合、遺言書に「○○に○○を相続させる」(「相続させる旨の遺言」と呼びます)と記載します。
- (2) <「相続させる旨の遺言」>は、「全部の相続財産を相続させる」とする場合と、「特定の財産を相続させる」(「特定財産承継遺言」(民1014条2項)とする場合があり、遺贈としてでなく、その遺言により相続の効力として相続人が相続財産を当然に承継します。
- (ア) 「相続させる」旨の遺言は、特段の事情のない限り「遺産分割方法の指定」であると解され、遺産分割手続を経ずに被相続人の死亡と同時に物権的効力が生じ、直ちにその遺産はその相続人に承継されます。
- a) 民法908条1項は「被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定め・・・ることができる」と規定しています。
- b) 「遺産の分割の方法を定める」とは、他の共同相続人と遺産分割の協議をしないで、その指定された相続財産が相続開始と同時に指定の相続人や受遺者のものになることです。
- c) 最高裁判例は、「相続させる」趣旨の遺言は、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、民法908条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、・・・このような遺言にあっては、何らの行為を要せずして被相続人の死亡の時に、直ちに当該遺産が分割されて当該相続人に相続により承継される、と判示しています(最判平成3、4、19 )。
- (イ) なお、民法改正(民法899条の2)により承継した相続財産のうち法定相続分を超える部分は、登記がなければ第三者に対抗できないとされています。
- (ア) 「相続させる」旨の遺言は、特段の事情のない限り「遺産分割方法の指定」であると解され、遺産分割手続を経ずに被相続人の死亡と同時に物権的効力が生じ、直ちにその遺産はその相続人に承継されます。
- (3) これに対し「遺贈」とは、遺言によって財産を贈る者(「遺贈者」)が相続人あるいは相続人以外の者(「受遺者」)に対し、財産上の権利義務の全部又は一部を無償譲渡することです。
- (ア) 「遺贈」は<遺言者の意思表示(遺言)によって権利(遺産の全部又は一部)を、無償または負担を付して他に譲与する(変動させる)>もので、<贈与のようなもの>と言われます。
- (イ) 遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」とがあり、受遺者には相続人以外の者も含まれます。
- a) 「遺言者は包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」(民964)。(但書(遺留分の規定に違反できない)は削除された。)
- b) 「包括遺贈」とは遺産の全部又は一部を一定の割合を示してする遺贈で、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」(民990)と規定されているので、従って遺産を当然かつ包括的に承継することになります。
- c) 「包括遺贈」は相続と異ならないので、従って他に包括受遺者又は相続人がいるときは、遺産は共有となります。
- (ウ) 「遺贈」による受遺者には、「割合的包括受遺者」と「遺産全部の包括受遺者」があり、前者の承認及び放棄は相続に準じ、後者は相続が開始すると遺産全部が直ちに受遺者に帰属するので、遺産分割の対象とはなりません(民964)。
- a) 他の相続人が相続を放棄した場合、割合的包括受遺者が相続人でないときは、遺贈される相続分の割合には影響を受けません。
- b) 全部包括遺贈については、遺留分侵害額請求の問題が生じるだけで、遺産分割の問題とはなりません。
- (エ) 遺言で<遺言者の介護にした相続人でない長男の嫁など>に自宅や預貯金等を取得させたい場合は、「遺贈」の遺言で財産を取得させます。
- (4) 遺言書で特定の相続人に不動産を取得させる場合は、取得させる不動産の全てを記載し、漏れのないよう注意を要します。
- (ア) 例えば遺言書に相続させる自宅敷地に付随する「私道」(「位置指定道路」など)の記載が漏れ(固定資産税が非課税で価値が小さいため)、その結果「私道」の遺産分割協議を要することが、予期せぬ紛争の種となる恐れがあります。
- (イ) もちろん、「一切の不動産を相続させる」とか、「上記の各財産以外の財産の全てを相続させる」等との記載がある場合は問題はありません。
- (5) また、遺言書には「予備的遺言」(補充遺言)を記載して置くことで、遺言の無効による遺産分割協議の対応を回避することができます。
- (ア) 「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」(民994Ⅰ)、「停止条件付の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも前項と同様とする。」(民994Ⅱ)と規定され、受遺者(相続人)が死亡すると遺言の「○○に○○財産を相続させる」とした部分が無効となり、○○財産については相続人全員による遺産分割協議を要することになります。
- (イ) 「但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」(民994Ⅱ但書)と規定されています。
- a) 受遺者(相続人)の死亡により受遺者に取得させる予定の財産の遺言はその部分が無効となり、それは相続人全員の遺産分割協議の対象財産となります。
- b) しかしながら、その場合でも遺言者が遺言で別段の意思表示をしておけば、その遺言が有効となります。この遺言を予備的(補充的)遺言と言います。
- 1) 予備的遺言は、遺言者が死亡するよりも前に受遺者(相続人)が死亡することを条件とする「条件付遺言」とされ、その場合予備的遺言において指定された者が受遺者(相続人)となります。
- 2) 例えば「妻○○が遺言者より以前に死亡したときは、妻に相続させるとした上記財産を遺言者の長男○○(○年○月○日生)に相続させる」などと、遺言書に新たな取得者を予備的に指定します。
筆者紹介

特別顧問
弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人
- 経 歴
- 宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」