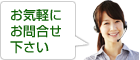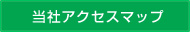相続対策と相続税対策について(その4)
2025.9.1
今回は「相続対策」(夫婦間での不動産の移転)についてお話しします。
- 7 「生前贈与」をすると、遺産分割の対象財産から外れるので、相続時のトラブル防止のメリットがあるが、場合によってはデメリットもあるので注意を要します。
- (1) 例えば、不動産(自宅)を配偶者に生前贈与すると、受贈者(配偶者)名義の財産になり、相続時には原則相続財産でなくなるので他の遺産から相続分を取得することができ、また、仮に相続放棄をしても自宅を失うことはありません。
- (ア) この「生前贈与」は「特別受益」(民903Ⅰ)に該当し、相続財産への持戻し(原則)となりますが、前回説明の通り、民法改正で「婚姻20年以上の配偶者への自宅の贈与」については、「持戻し免除の意思表示の推定規定」(民903Ⅳ)が新設され、その適用により遺産分割対象から外すことができます。
- (イ) 但し、他の相続人が遺留分侵害額請求をした場合は、原則加算されますがこれも民法改正で、贈与が相続開始より10年前であれば加算されないことになったので(民1044Ⅲ)、自宅を生前贈与する場合は、時期を考えることが重要です。
- (2) 「居住用不動産の配偶者控除」を活用すると、税法上、将来の相続財産を減らすことで相続税の節税効果を生じさせることができます。
- (ア) 「配偶者控除の特例」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又はその取得のための金銭が贈与された場合、贈与税の申告をすると基礎控除額110万円に加え最高2,000万円まで控除することができる制度です。
- a) 受贈した翌年3月15日までに、取得した居住用不動産又は金銭で取得した居住用不動産に受贈者が現実に居住し、引き続き住む見込みであることを要する。
- b) 同じ配偶者から一生に一度しか配偶者控除の適用を受けることができない。
- (イ) 居宅兼店舗の生前贈与等があった場合に店舗部分の処理、相続させる旨の遺言の場合に持戻し免除の意思表示の推定に関しては、必ず専門家に相談して下さい。
- (ウ) 贈与する居住用不動産と同じ敷地内に、居宅以外に「事業用部分(農作業用の作業小屋など)」(特例の適用不可)があれば、分筆登記をして用途を区分する。
- (ア) 「配偶者控除の特例」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又はその取得のための金銭が贈与された場合、贈与税の申告をすると基礎控除額110万円に加え最高2,000万円まで控除することができる制度です。
- (3) 不動産は、例えば自宅の持分を数年に分割して贈与し、110万円の基礎控除を活用する方法もあり、それによって贈与税を抑えられます。
- (ア) しかし、贈与者が亡くなった場合は、相続税で贈与を受けた日から7年以内の生前贈与分が、相続財産に持ち戻して加算されます。
- a) 改正後の7年ルールが適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与である。
- b) 毎年一定金額の贈与をする場合に「定期贈与」とみなされると、その全部に贈与税が課税されるので、贈与の都度「贈与契約書」作成等の対応を要する。
- (イ) また、贈与の都度、登録免許税や諸費用などがかかるので注意を要します。
- (ア) しかし、贈与者が亡くなった場合は、相続税で贈与を受けた日から7年以内の生前贈与分が、相続財産に持ち戻して加算されます。
- (4) 生前贈与のデメリットは「登録免許税」「不動産取得税」が高い上、固定資産税等の維持費の支払を要するので、贈与税は抑えられてもそれ以外の費用が高額になることがあるので事前の検討を要します。
- (1) 例えば、不動産(自宅)を配偶者に生前贈与すると、受贈者(配偶者)名義の財産になり、相続時には原則相続財産でなくなるので他の遺産から相続分を取得することができ、また、仮に相続放棄をしても自宅を失うことはありません。
- 8 「相続」のメリット・デメリットについて見てみます。
- (1) 不動産を「相続」で取得する場合のメリットは、「配偶者控除」の枠が大きく非課税になる場合がほとんどで、仮に「相続税」が課税される場合でも「贈与税」より基本的に低くなる可能性があります。
- (ア) 相続税での配偶者の税額を軽減する「配偶者控除」制度は、<課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(1/2)>、または<1億6,000万円>のどちらか多い金額が控除額となり相続税がかかりません。
- (イ) 従って、殆どの場合は配偶者控除の枠を利用すれば、不動産の相続税額は非課税になり、「相続税」が課税となる場合でも原則「贈与税」より安くなります。
- (2) また「小規模宅地等の特例」、すなわち相続や遺贈による取得財産のうち、相続開始の直前に被相続人の居住用の宅地等(土地又は土地上の権利)のうち、一定の面積について相続税の課税価格に算入すべき価額を一定の割合で減額できます。
- (ア) 「小規模宅地等の特例」は、土地の評価に関する特例で、例えば自宅の相続税の評価額を80%、その他の場合は50%減額できるのです。
- a) <相続人で利用可能な者>は、配偶者、一緒に住んでいた同居家族、3年以上賃貸や社宅に住んでいる別居家族であり、限度面積は330㎡までである。
- b) 居住用の判定は、住民票での形式的判断でなく実際の居住を要する。
- c) 土地評価額が「基礎控除3,600万円」までは、税金はかからない(上記(1))。
- (イ) 「小規模宅地等の特例」の適用は「個人が相続または遺贈で取得した財産」に限られ、生前贈与で取得した不動産は、相続財産に含まれる場合でも適用されない。
- a) 贈与を受けた日から7年以内に贈与者が亡くなり、生前贈与分が相続財産に加算(持戻し)される場合は、「小規模宅地等の特例」は適用できない。
- b) 「居住(保有)継続要件」があり、相続税の申告期限が過ぎるまでは売却できなくなり、申告期限を待たずに売却すると80%の減額が取消しとなり、その取消し部分に対し過少申告加算税・延滞税がかかる。
- c) 但し<相続人が配偶者の場合は、「居住(保有)継続要件」がない>ので、売却時期の制限がなくいつでも売却できる。
- 1) 配偶者は、被相続人の居住用だけでなく、被相続人以外の生計一の親族(例えば長男)の居住用を取得した場合も特例を適用できるが、同要件は要する。
- 2) なお、配偶者が事業用宅地(特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地)を相続する場合は「保有継続要件」があるので要注意。
- d) 相続不動産の売却が、相続開始から3年10か月以内であれば、相続税額の一定金額を譲渡資産の取得費(B)に加算し、「譲渡所得税」の引下げができる。
- ※「譲渡所得税」={不動産の売買金額(A)-不動産を取得した金額(「取得費加算」)(B)-諸経費(C)}×20% (国税庁No.3267参照)No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
- (ア) 「小規模宅地等の特例」は、土地の評価に関する特例で、例えば自宅の相続税の評価額を80%、その他の場合は50%減額できるのです。
- (3) 不動産相続のデメリットは、遺産分割協議による場合は分割方法(「換価分割」、「現物分割」、「代償分割」(一人が取得し他に金銭等を支払う)、「共有分割」)が難しいので、遺言により取得方法を定めておくのが最善です。
- (4) 以上の通り、「相続」の方がベターな場合が多く、「生前贈与」を利用するのは例えば「前妻の子でなく後妻に自宅を取得させたい場合(婚姻期間が20年以上、遺留分の持戻しが想定されない(贈与者が10年後存命))」や「負債が大きく相続人が相続放棄をする場合」(但し、生前贈与が詐害行為に該当しないこと)などである。
- (1) 不動産を「相続」で取得する場合のメリットは、「配偶者控除」の枠が大きく非課税になる場合がほとんどで、仮に「相続税」が課税される場合でも「贈与税」より基本的に低くなる可能性があります。
筆者紹介

特別顧問
弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人
- 経 歴
- 宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」