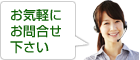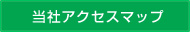会社経営者の事業承継について考えてみましょう(その19)
2022.9.1
今回は、前回に引き続き「円滑化法」(民法の特例)の「事業承継者の要件」等について話します。該当要件等の話は面白味がありませんが、(その18)に戻って読み直し「民法の遺留分に関する特例」の重要性を再確認してから、その要件に目を通してみましょう。
-
1 適用対象となる事業承継者(主体)に関する要件については「その14」でも説明していますので参照下さい。
-
(1) 「特例中小会社」(「特例中小企業者」)の要件(法3Ⅰ)。
- (ア) 中小企業者(会社又は個人)(法2)の事業承継だけに限ります。
- (イ) 3年以上継続して事業を行っていること(施行規則2)。
- (ウ) <会社の場合>は、先代経営者が後継者に生前贈与等により株式を承継させた場合に適用対象となります。
- (エ) <個人事業者の場合>は、後継者が先代経営者から贈与等によって取得した事業用資産の承継(①土地、②建物、③減価償却資産)が対象となります。
-
(2) 「旧代表者」(先代経営者、被相続人)の要件(法3Ⅱ)
-
(ア) 特例中小企業者の元代表者又は現代表者であること。
- (イ) 推定相続人のうちの1人に対して株式等を贈与したこと。
-
- (3) 「後継者」(推定相続人)の要件(法3Ⅲ)
-
(ア) 後継者は、特例の適用を受ける時点で特例中小企業者の代表者であること。
- (イ) 旧代表者から特例中小企業の株式等を贈与により取得した者であること。
(当該贈与を受けた者から当該株式等を相続、遺贈、贈与により取得した者でも良い) - (ウ) 株式の贈与により、総株主の議決権の過半数を有すること(議決権要件の充足)
- a) 贈与を受ける前の時点で、議決権の過半数の株式等を保有していないこと。
- b) 旧代表者が総株主(全部事項無議決権株式の保有者を除く)。又は総社員(特例合意対象株式等を含めて)の議決権の過半数を有すること。
-
-
-
2 特例合意の内容は、次の通りです。
- (1) 特例は親族内の「先代経営者から子(配偶者)への生前贈与による承継」だけを対象としており、遺言は除かれます。
- (ア) 事業承継に不可欠な自社株式等にかかるものでなければならない。
- a) 複数回で贈与されても1回の合意の対象とすることができる。
- b) 贈与契約をしても株式の移転をしていない場合は適用がない。
- (イ) 特例合意は、法の施行後のものだが、財産の贈与等は法施行前のものでも良い。
- (ウ) 遺留分侵害額請求を事前に防止し、後継者貢献による株価上昇分を保持できる。
- (ア) 事業承継に不可欠な自社株式等にかかるものでなければならない。
-
(2) <現経営者の兄弟姉妹>や<役員従業員等が親族でない者>への承継の場合は、兄弟姉妹は遺留分権がないので「民法の特例」の適用はありません。
- (ア) 非親族への事業承継は、通常株式等の売買で行われる。
- (イ) 株式等の「生前贈与」は、遺留分侵害額請求の対象となるが、特別受益でないので相続開始前1年間にしたものに限られ(民1044)、また、遺留分権は相続の開始の時から1年間行使しないときは時効によって消滅する(民1048)。
- ※「特別受益」とは、相続人が被相続人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組・生計の資本等として生前贈与を受けた場合の利益を言う。
- (ウ) なお、改正民法は「遺留分侵害額請求」を遺留分に相当する金銭の支払を請求できる権利とした(民1046条)。
- a) 改正前の遺留分減殺請求の場合、株式等が他の相続人と共有状態となったので財産の処分が困難になり、新たな紛争を引き起こし事業承継に支障が生じた。
- b) 改正法はこの弊害を回避したが、後継者は金銭支払のために資金繰りを必要とするので、支払準備ができない時は、裁判所に金銭債務の全部又は一部について支払期限の猶予を求めることができるとされている(民1047条Ⅲ)。
- (1) 特例は親族内の「先代経営者から子(配偶者)への生前贈与による承継」だけを対象としており、遺言は除かれます。
筆者紹介

特別顧問
弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人
- 経 歴
- 宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」。