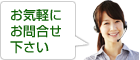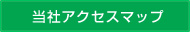18. 前回に引き続いて、「特例措置」の「都道府県知事の認定」の要件等につき説明します。
やや複雑ではありますが、贈与税・相続税を「0」にする方法ですので、次回以降も含めてお付き合いください。
「特例措置」に関心ある方は、専門家にご相談ください。
【Ⅱ】 「新事業承継税制」(「特例措置」)には「法人版」と「個人版」とがあり、後継者は<法人版の場合は>非上場
会社の株式等を、<個人版の場合は>事業用資産を、先代経営者等から贈与・相続により取得した場合に、「都
道府県知事の認定」を前提に、贈与税・相続税の納税の猶予又は免除されます。
1 <法人版の「特例措置」の適用>に関する手続は、次の通りです。
- (1) 「法人版事業承継税制」に「特例措置」と「一般措置」の2つの制度があります。
- (2) 「特例措置」は、下記の通り、事前の計画策定等や適用期限が設けられ、適用期限を平成30年1月1日から10年間に
限定し、納税猶予の対象株式数の制限(総株式数の3分の2まで)を撤廃して全株式とし、また納税猶予割合を
(80%から100%に)引上げる等しました。
- (ア) < 「特例措置」の主な要件>は次の通りです。
- a)(事前の計画策定等)5年以内(平成30年4月1日から令和5年3月31日まで)に「特例承継計画」を提出
- b)(適用期限)上記の10年以内(令和9年12月31日まで)の相続等・贈与等
- c)(対象株数)全株式
- d)(納税猶予割合)100%
- e)(後継者)最大3人
- f)(雇用確保要件) 承継後5年間(平均8割の雇用維持要)につき例外がある(雇用確保要件を満たさない場合
は、円滑化法施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさい理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出
し、その確認を受ける必要がある。)
- g)(事業継続に困難な事由が生じた場合の免除)譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し,従前の
猶予税額との差額を免除。
- h)(相続時精算課税の適用)贈与者(60歳以上)から受贈者(20歳以上)へ
- (イ) まず令和5年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて「特例承継計画」を作成し、都道府
県知事に提出して確認書の交付を受けます。その提出前に先代経営者が死亡した場合には、死亡後の「特例承継計
画」の提出も認められます。
- (ウ) 「特例承継計画」の提出後、① 令和9年12月31日までに先代経営者が代表者を退き、② 後継者が代表者に就任
し、③ 株式を後継者に一括で贈与します。
- a)適用期限は平成30年1月1日から令和9年12月31日までとされ、後継者が贈与・相続(遺贈を含む)により自社
の株式等を取得することが必要です。
- b)贈与した年の10月15日から翌年1月15日までに都道府県知事に認定申請をして、会社要件、後継者の要件、先
代経営者等の要件を充足している「認定書」の交付を受けます。
1) 先代経営者以外の株主(先代経営者の配偶者、兄弟など)から後継者への株式の贈与・相続の追随も認めら
れます。
2) 但し、それらの追随認定は、認定後5年間の有効期間内に申告期限が到来するものに限って受けることがで
きます。
- (エ) 後継者は、翌年3月15日までに認定書の写し等を添付した贈与税の確定申告書を税務署へ提出し、納税が猶予され
ます。
- (オ) 猶予される贈与税額とその利子税額に見合う担保を国(税務署)に提供することを要します。
- a)担保提供を認める財産は、不動産、国債、地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認め
る保証人の保証等です。
- b)納税猶予の対象となる特例非上場株式(譲渡制限株も可)等の全部を担保提供した場合には、その「見合う担
保」の提供があったものとみなされます。
- (3) 「特例経営承継期間」(5年間)は毎年、その経過後、猶予期間中は3年ごとに税務署に「継続届書」を提出し、また都
道府県知事に一定の書類の提出を要します。
- (4) その後、先代経営者が死去し相続が発生した場合に次の手続を必要とします。
- (ア) 死亡日から6か月を経過する日までに「免除届出書(死亡免除)」を相続税納税地の所轄税務署長に提出を要しま
す。
- (イ) 相続開始の日から8か月以内に都道府県知事に「贈与から相続」への切替の申請をします。
- (ウ) 相続開始日から10か月以内に相続税の納税猶予及び免除の特例を受ける旨の相続税申告書と一定の書類を税務署
に提出します。この時も、猶予される相続額及び利子税額に見合う担保提供が必要となります。
- (エ) この時点で猶予されていた贈与税が免除され,相続税の猶予が始まります。
- (5) 後記の通り、先代経営者は相続発生時点で役員であること、後継者は相続開始の直前に役員であり、相続開始から5
か月後に代表者であることを必要とします。
2 「個人版事業承継税制」は、平成31年度税制改正で、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で多様な事
業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する制度として創設されました。
- (1) 青色申告(正規の簿記の原則による)をする事業(不動産貸付事業等を除く)を行っている先代経営者から、
後継者が円滑化法の認定を受け、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合に、一定の要件のもとに
贈与税・相続税の猶予と、後継者の死亡等によりその免除を受けることができます。
- (2) 円滑化法の認定等を受けるには、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに都道府県知事に「個人事業承継計画」
を提出し、確認を必要とします。
- (3) 平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間に、贈与・相続(遺贈を含む)により事業用資産を取得するこ
とが必要です。