遺言書のきほん(総括)
2024.7.22
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回で遺言書のきほんのお話しは最後となります。これまでお話ししたポイントをまとめると…
●遺言書の作成は、公正証書遺言をお勧めします
●遺言書作成の目的・趣旨を軸とすることが大切
●自筆証書遺言についての改正内容を把握しておく
●公正証書遺言の作成は、まずは打ち合わせから
●遺言書の内容は、専門家に相談してから決めましょう

2024.7.22
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回で遺言書のきほんのお話しは最後となります。これまでお話ししたポイントをまとめると…
●遺言書の作成は、公正証書遺言をお勧めします
●遺言書作成の目的・趣旨を軸とすることが大切
●自筆証書遺言についての改正内容を把握しておく
●公正証書遺言の作成は、まずは打ち合わせから
●遺言書の内容は、専門家に相談してから決めましょう

2024.7.15
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
遺言書があっても揉めてしまうことはあります。どんな準備をしておくべきか確認しておきましょう。
遺言書を使う場面を考慮する
①相続人が遺言書を見つけられるようにする
・保管場所を信頼できる相続人に伝えておく
・貸金庫に保管しない!
②相続人が遺言書を読んだときの受け止め方へ配慮する
・人は感情の生き物、相続で揉める原因は感情面での行き違いがきっかけであることが多い
・遺言書があっても揉めてしまう場合もある
特に、特定の相続人の遺留分を侵害せざるを得ない場合、相続人間のバランスを欠かざるを得ない場合
・・・付言や遺留分問題の準備などでフォローが欠かせません
➂使いやすい遺言書を作成する
・あいまいな内容は書かない
・不動産の名義変更・・・法務局で登記をするため、様式に則って記載
登記簿謄本で確認する(住所ではなく地番、家屋番号を記載)
・金融機関の名義変更・・・金融機関名・支店名までの記載で十分
・書かれていない資産を、包括的に相続する人を決める一文を入れる
【注意】遺言書に記載のない遺産は、何も触れられていない場合、「遺産分割協議」をしないと受け継ぐことができません
2024.7.8
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
前回(その13)の続きです。
公正証書遺言の作成 ~進め方~
➂証人2名を手配
・利害関係のない2名を証人として選ぶ
〈証人になれない人〉・・・推定相続人、推定相続人の配偶者・直系血族、財産をもらう人、未成年者など
・公証役場で紹介してもらうこともできる(日当必要)
④公正証書遺言の作成
・遺言者が口頭で内容を述べ、公証人が筆記する
・遺言書の作成後、公証人が記載内容を読み聞かせる
・遺言者、証人が署名押印する(原本) ※遺言者は実印、証人は認印で押印
⑤完成
・原本は公証役場に保管されます
・正本、謄本は遺言者に渡されます
・公証認への手数料は、財産の額や分け方によって算出、完成時に支払います
「公正証書遺言検索システム」
公証人であれば、被相相続人の遺言の有無や保管のある公証役場がどこかを、全国どこの公証役場からも照会できます
2024.7.1
第5回は相続税対策の一つとして「都度贈与」について見ておきましょう。「都度贈与」は聞き慣れないかもしれませんが、皆さんが常々行っている家族の生活や教育を支える贈与の仕方です。後継者の育成に役立つ大事な資金の投資にもなります。
【第5】「贈与税」(相続税法21条以下)には「非課税財産」(相続税法21条の3)の一つとして「都度贈与」があり、それは生活費又は教育費について扶養義務者から必要の都度に贈与を受ける場合を言い、その目的のために1回で全額使い切ってしまえば贈与税はかからない制度です。
(1)<相続税法21条の3(贈与税の非課税財産)>
2 生活費や教育費としての「都度贈与」には譲渡金額の上限は設けられていませんが、その使途目的から自ずと限度があることを弁えておく必要があります。
(2) 「都度贈与」の非課税は、あくまでも必要に応じて実施した場合で、将来の分まで渡すと全額を教育に使ったとしても非課税の対象外になりますし、教育資金として渡したのを、他の用途に使った場合も贈与税を課せられます。

弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人
2024.6.22
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
公正証書遺言は、公証人が原稿を作成してくれます。自筆証書遺言とは作成の流れが異なりますので確認しておきましょう。
公正証書遺言の作成 ~進め方~
①公証役場に原案を持参し、公証人と打ち合わせ
・全国どこの公証役場でも作成できる
・自宅や病院、施設への出張も可能(都道府県内のみ)
②必要書類を集める
・遺言者の印鑑証明書(作成日の3ヶ月以内に取得したもの)
・遺言者と財産を取得する人との関係がわかる戸籍謄本
・不動産がある場合・・・登記簿謄本と固定資産税評価証明書など
| 必要書類は遺言者の内容により異なるため、公証人と打ち合わせをして確認しましょう |
2024.6.15
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回は、自筆証書遺言の保管制度についてお話しします。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が、2020年7月10日から始まりました。保管制度を利用すると遺言者の死亡後、家庭裁判所での「検認」手続きは不要になるため、速やかに相続手続きができるようになりました。他にもメリットとして以下の点が挙げられます。
・自筆証書遺言の要件が満たされているか法務局で確認してもらえる
・遺言書の紛失、破棄や改ざんが行われるおそれがなくなる
遺言者の死亡後は「遺言書情報証明書」を取得し、各種相続手続きをします。
法務局では、遺言の内容自体についての相談にはのってもらえません(遺留分の問題、相続税の特例が適用できるかなど)。また、遺言をするときには遺言能力を有することが必要とされていますので、遺言能力がない状態で作成された遺言は無効となります。
遺言能力・・・自分のする遺言の内容及びその結果を理解し判断できる能力
➡➡ 専門家に相談+公正証書遺言の作成をお勧めします
2024.6.8
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
相続法の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン等で作成できるようになりました。そのため作成する手間がかなり減ることになりました。
銀行通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書などを財産目録として遺言書に添付することもできます。
ただし、パソコンで作成した財産目録には、全ページに署名・押印が必要です。偽造、変造(財産目録だけ差し替える等)を防ぐため、相続人間のあらぬ疑いの種にならないよう実印での押印と割印をお勧めします。
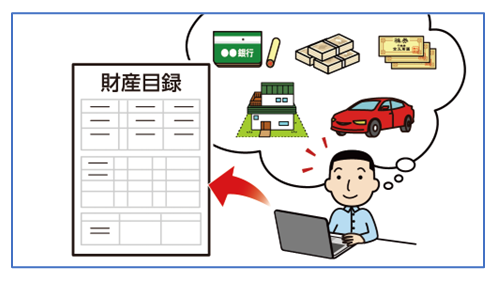
2024.6.1
第4回は、<暦年贈与>と<相続時精算課税制度>を活用する際の選択の方法について見て行きましょう。
(2) <事例2> 相続開始前の10年間、毎年300万円贈与した場合

弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人
2024.5.24
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
自筆証書遺言は、方式が厳しく決められています。
せっかく作成した遺言書が無効となることのないよう、法的な要件を確認しておきましょう。
自筆証書遺言を作るときの注意点
①内容は全て自分で書く
遺言者本人がすべて自筆(手書き)で書きます。パソコンで作成したり(財産目録は可)、録音、録画、家族等による代筆は無効になります。
②作成した日付を正確に書く
「令和6年5月1日」「2024年5月1日」等と正確に書きます。「令和6年5月吉日」とは書きません。
➂署名・捺印が必要
戸籍上の氏名をフルネームで書きます。印鑑は認印でも構いません。
④加除・訂正は様式に従う
書き加えたり、訂正をした箇所を示し、変更した旨を書き添えて署名、変更箇所に押印します。
⑤相続後に分かる場所で大切に保管
遺言書の入った封筒は、糊付けをしていなくても大丈夫です。
2024.5.17
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
ステップ3では、遺言書を作成します。
ステップ3 遺言書を作成する
▶自筆証書遺言の場合
・自筆ですべて記載する
・相続法改正により、2019年1月13日から財産目録は自筆ではなく、パソコン等でも作成可能 ※財産目録すべてに署名押印
・自筆証書遺言の保管制度の利用も検討
▶公正証書遺言の場合
・公証役場に行き、公証人と打ち合わせ
・必要書類を収集
・証人2人の立会いのもと作成
・遺言の原本は公証役場で保管、正本と謄本を手元で保管