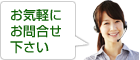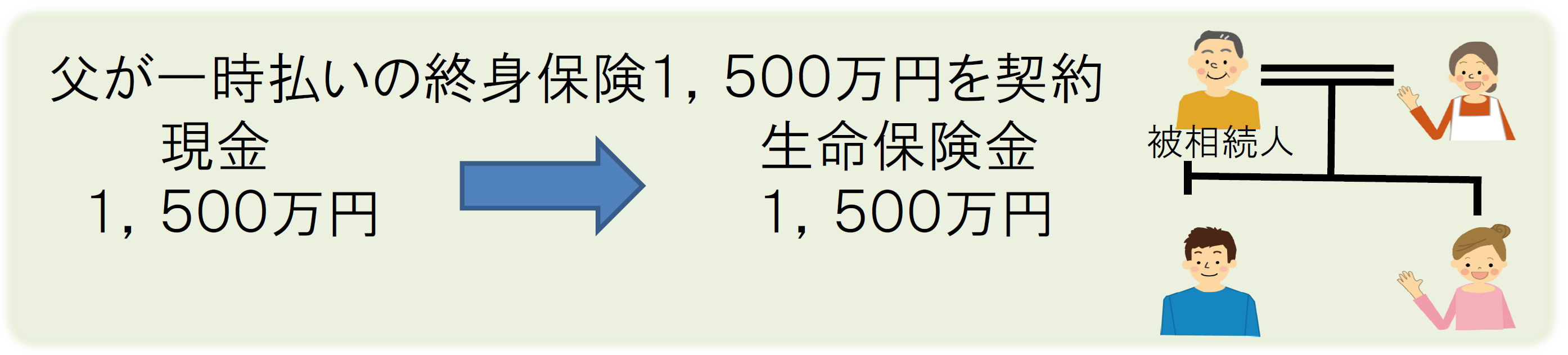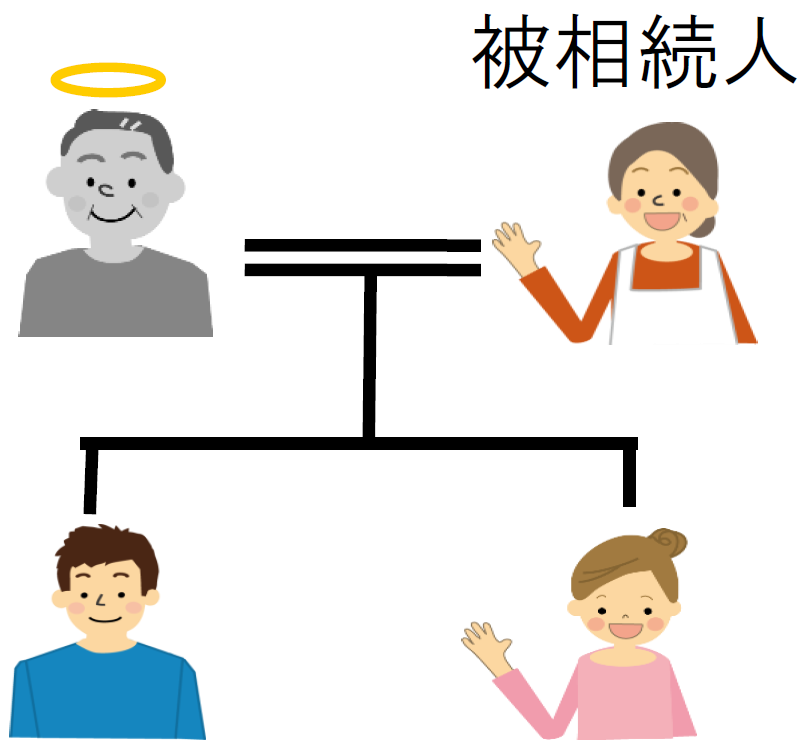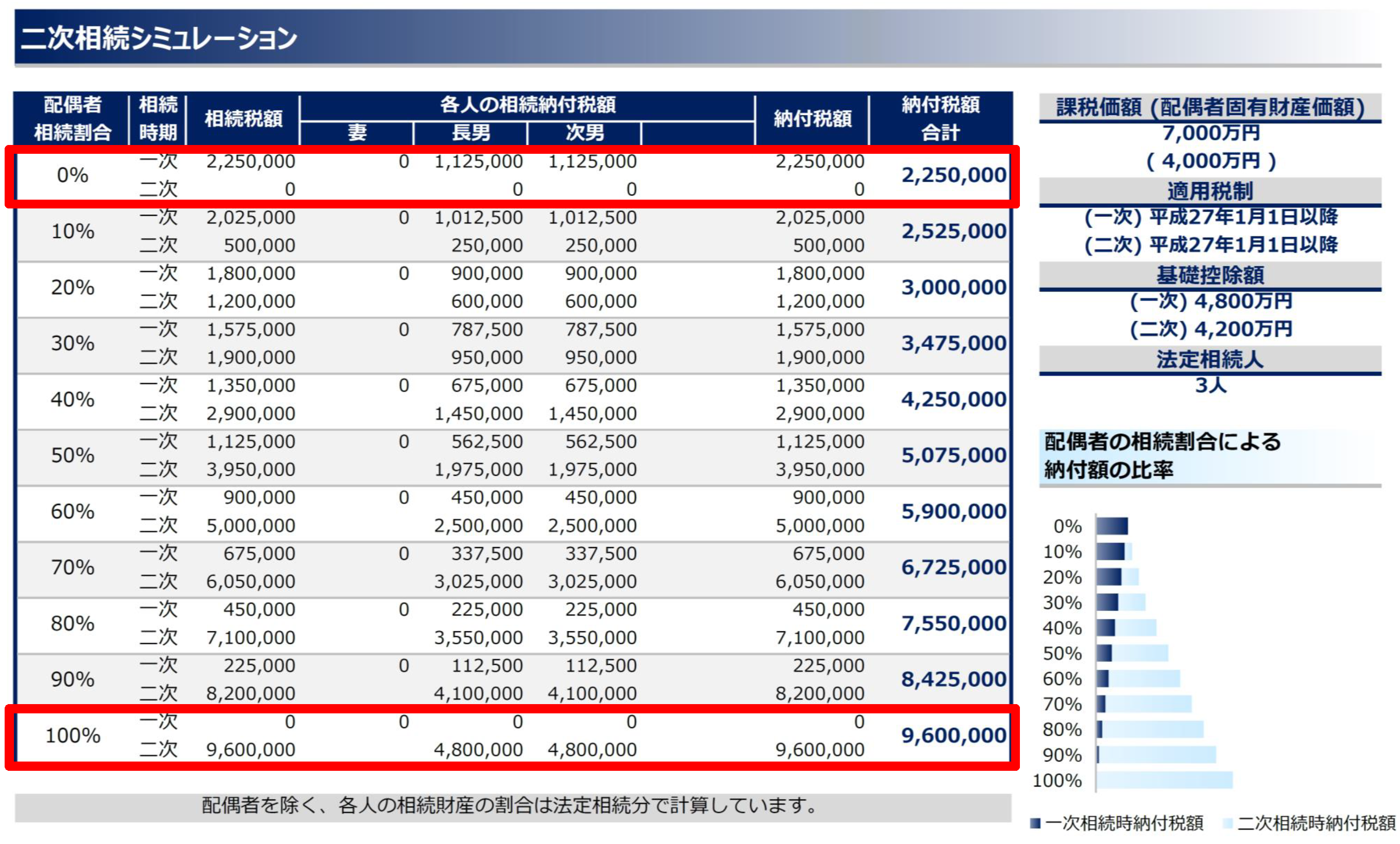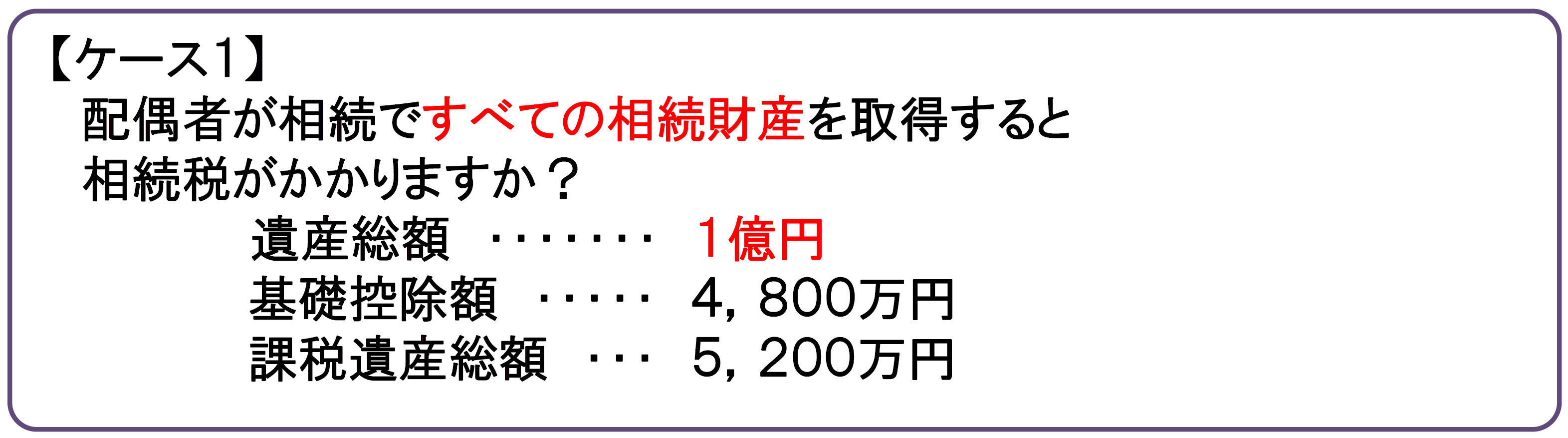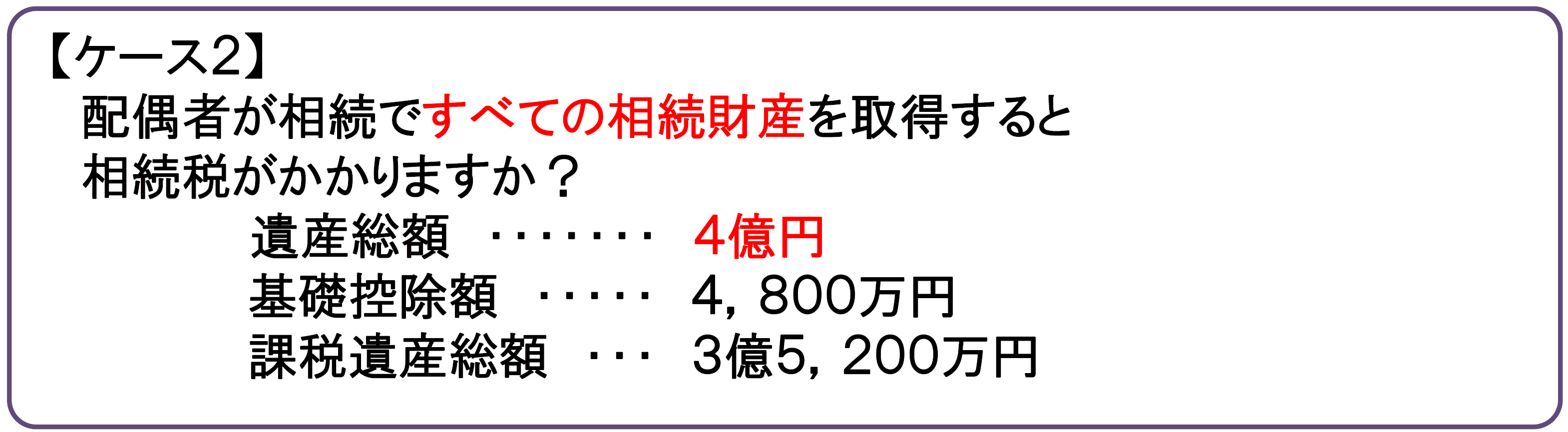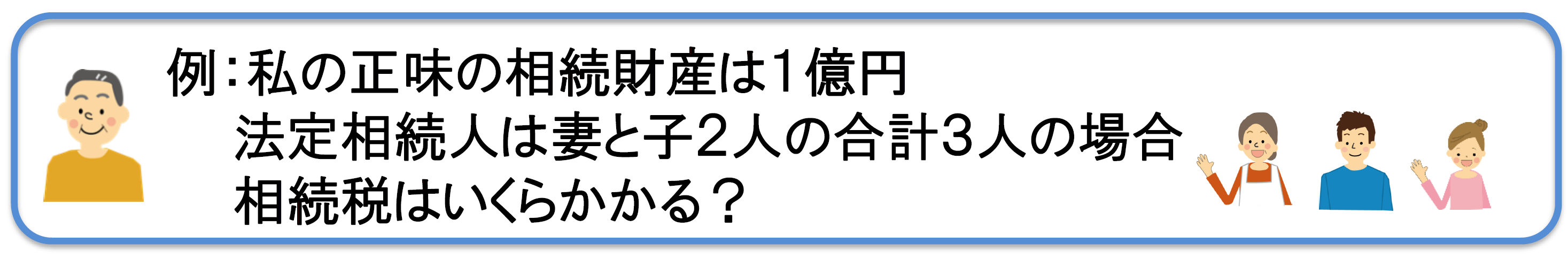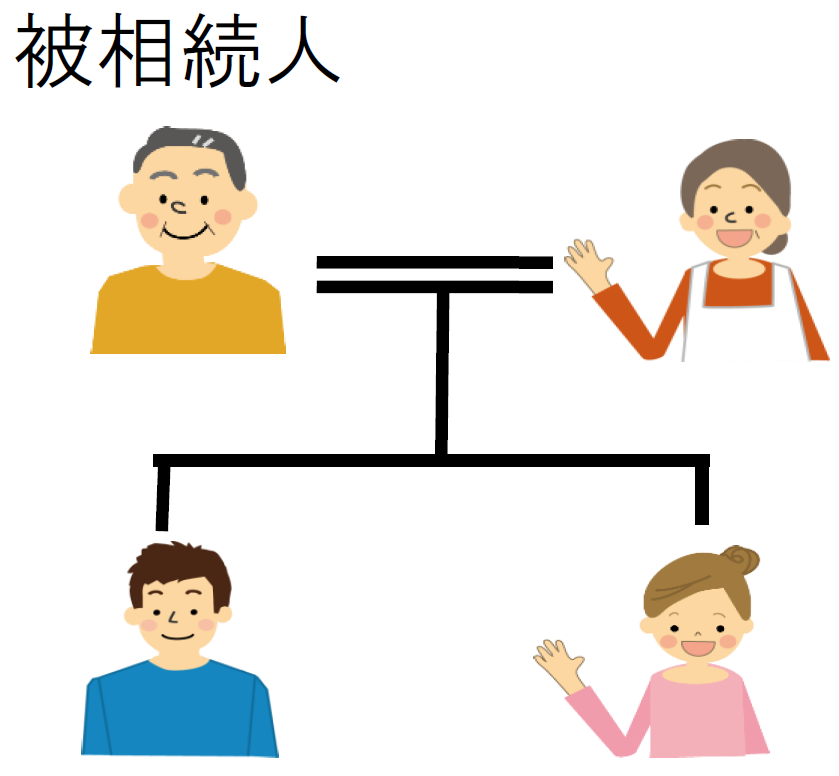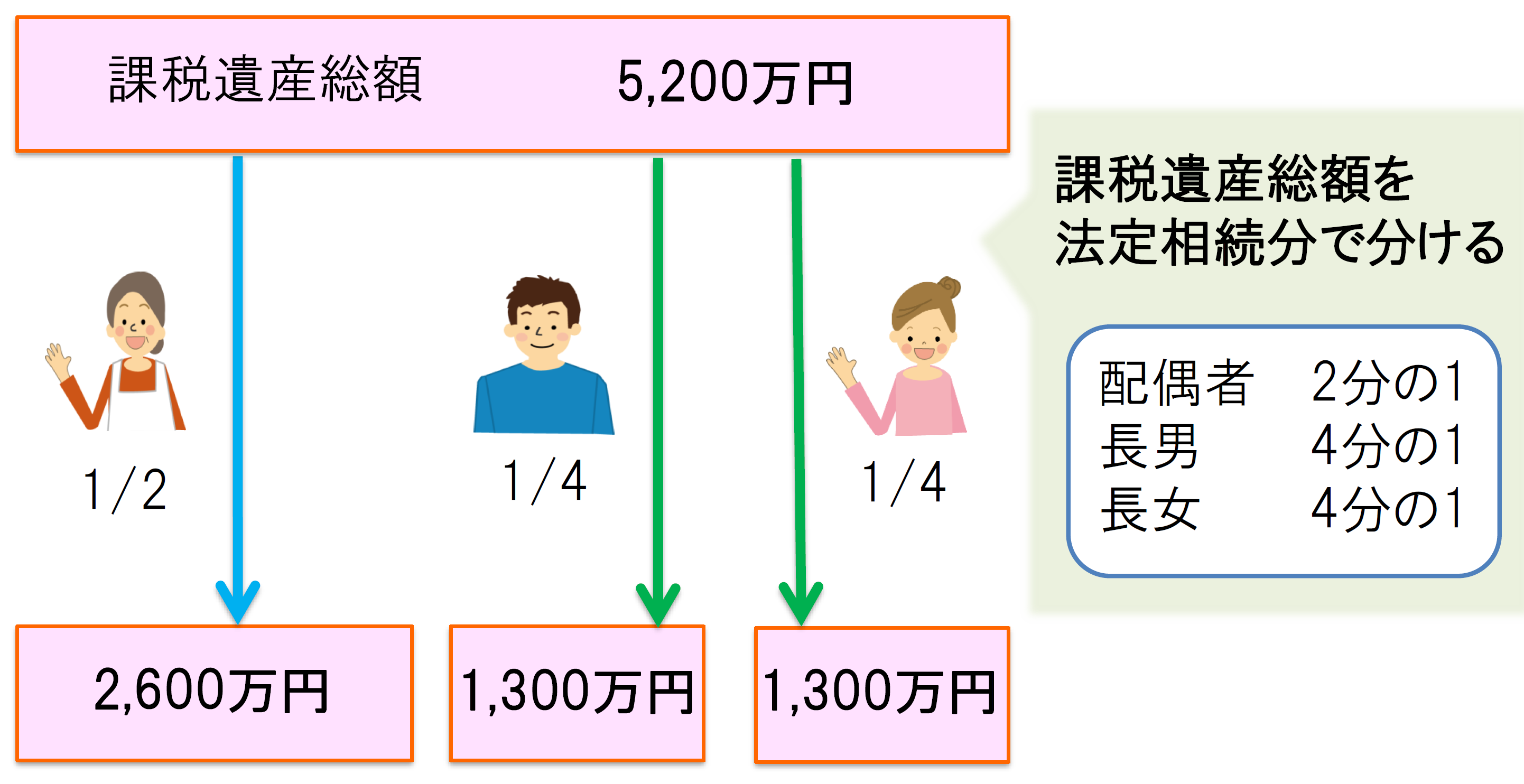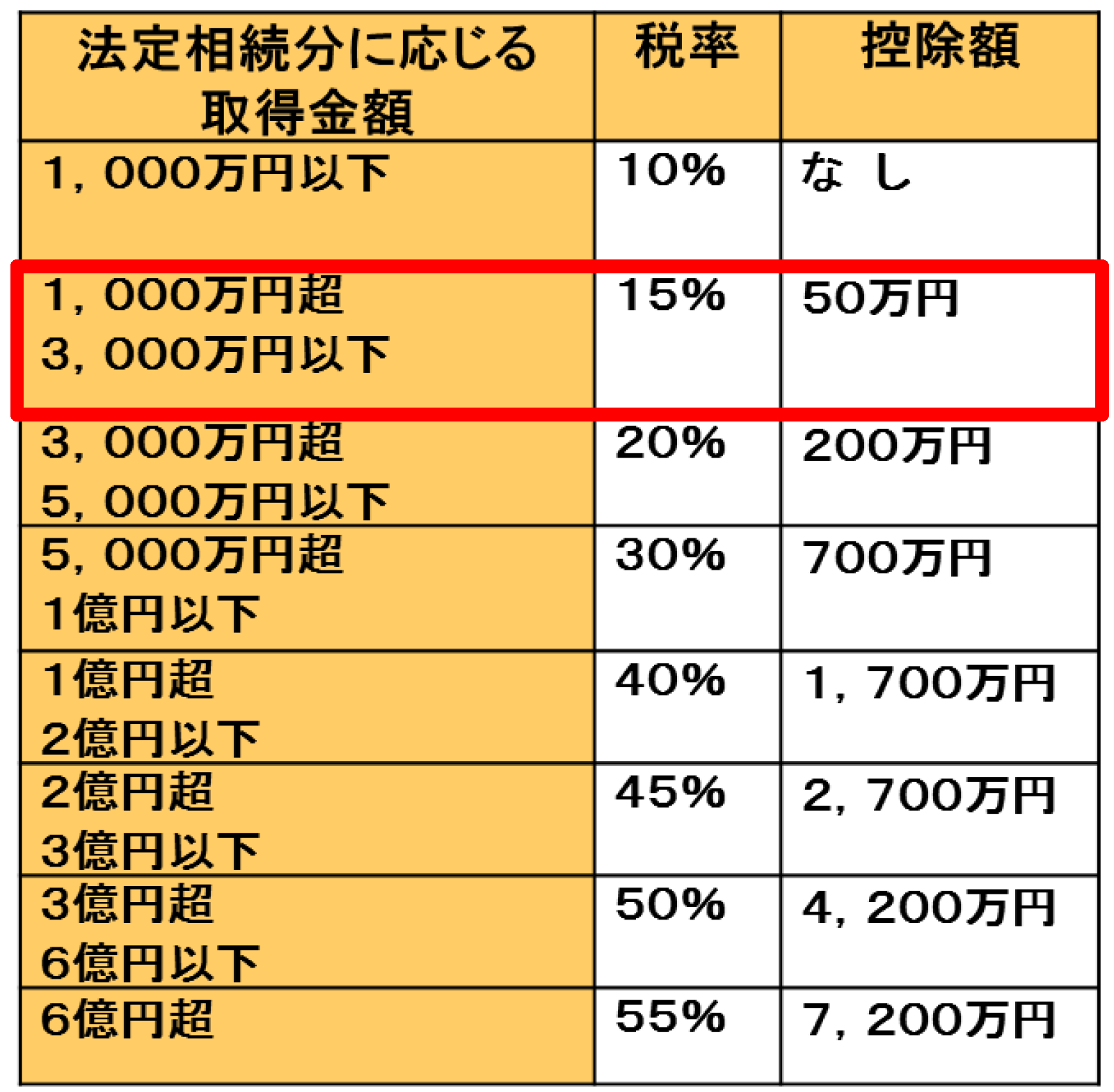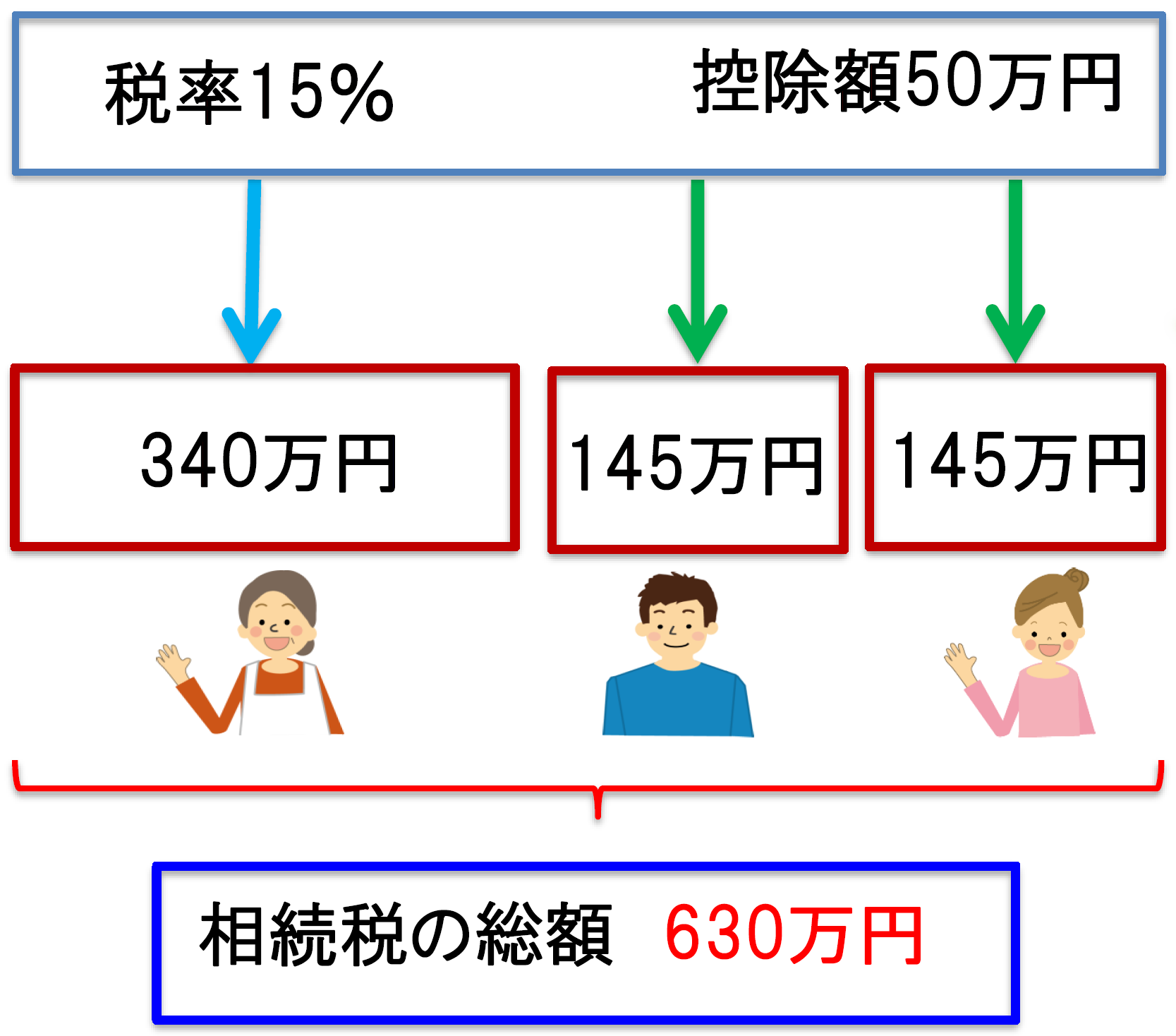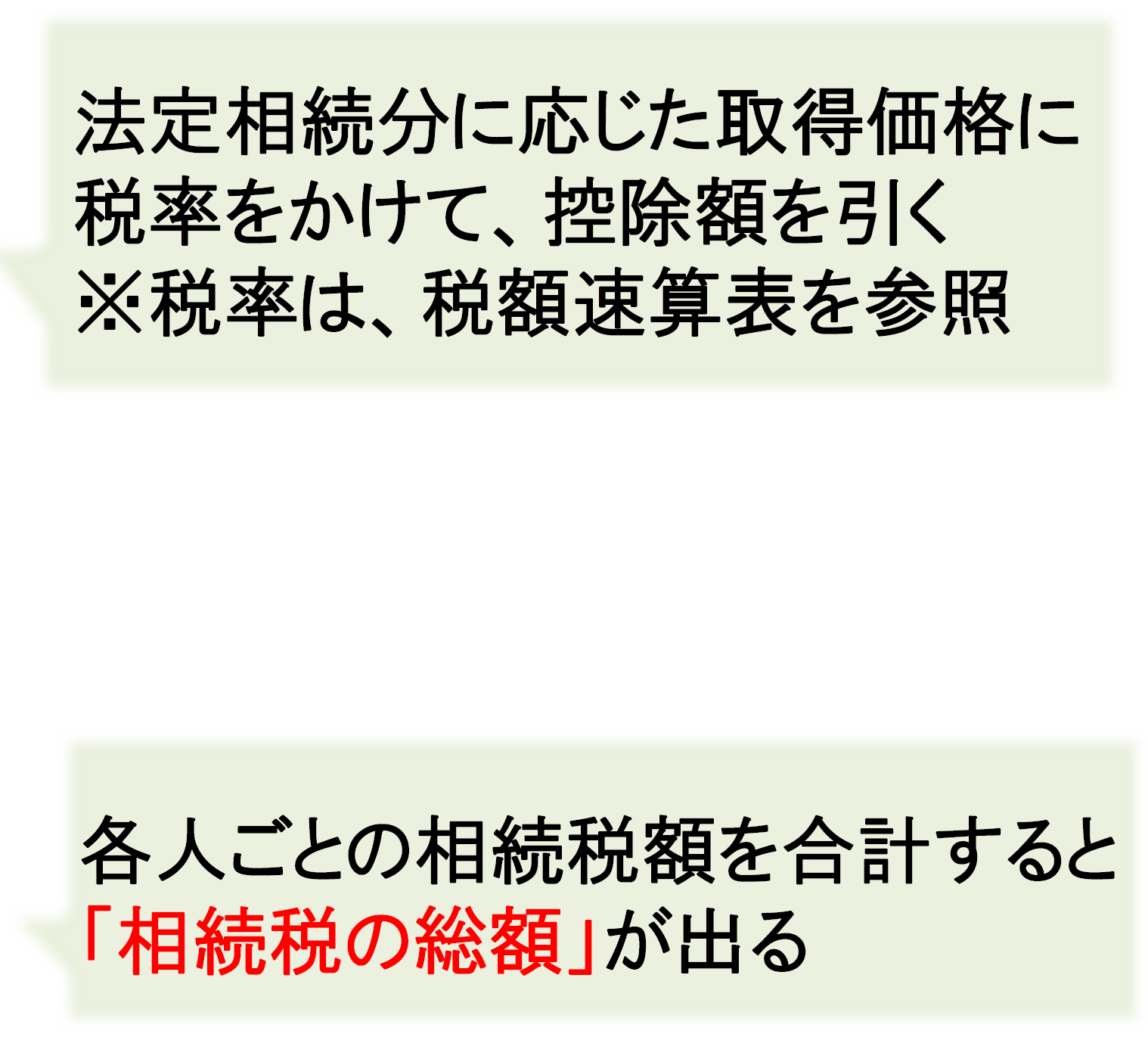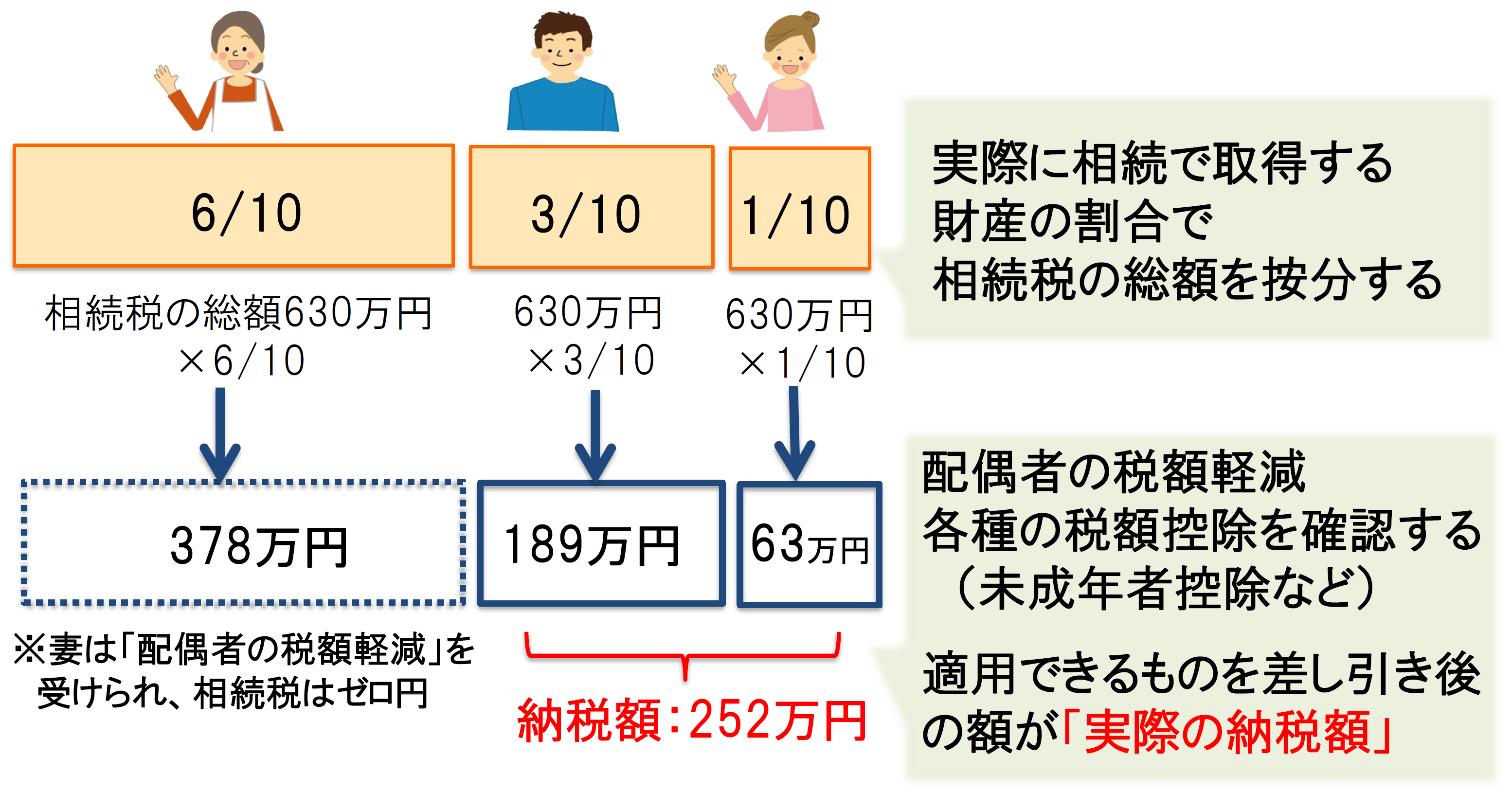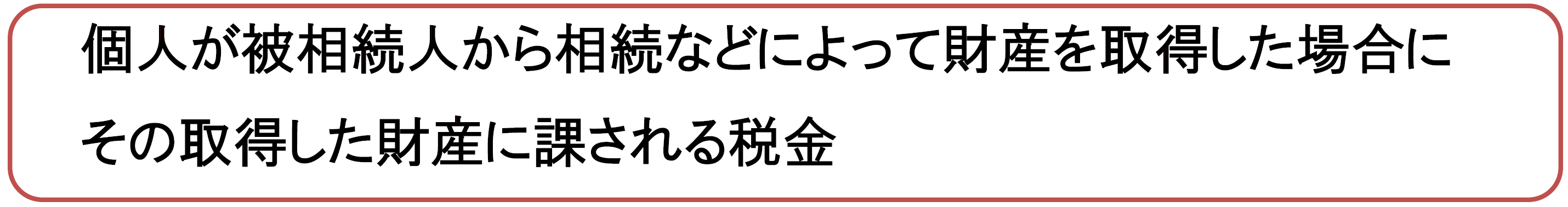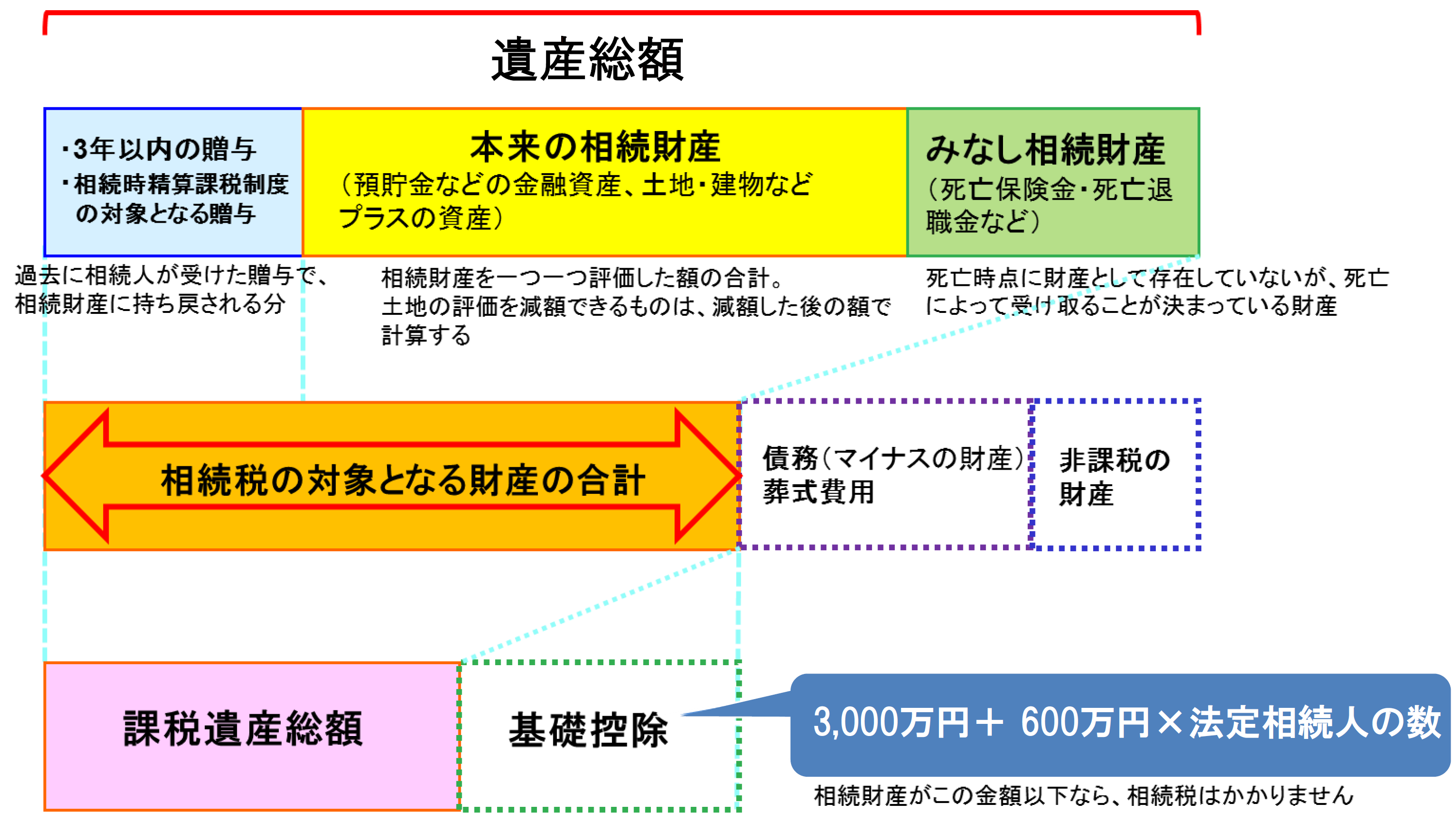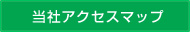相続税のきほん(その7)
2023.11.9
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回から相続財産の評価方法についてお話しします。
おさえておきたいポイントは次の3つです。
①それぞれの相続財産の評価方法
▶ポイント…難しいけれど特に知っておきたい不動産の評価方法
②自宅の評価が8割減額!「小規模宅地等の特例」
▶ポイント…自分や親の相続の際に特例を使える?
③評価方法からわかる相続税の対策
▶ポイント…自分や親の相続に備えてこれからできる対策は?
それでは順番にご説明していきます。
①それぞれの相続財産の評価方法
1.金融資産の評価方法
| 現金 | 相続発生日に存在した金額(財布、金庫など) |
| 預貯金 | 相続発生日の残高の合計額
相続申告日は、税務署には残高証明書を提出
|
| 上場株式 | 次のうち、最も低い金額で評価
①相続開始の日の最終取引価額 ②相続開始の月の最終取引価額の月平均額 ③その前月の最終取引価額の月平均額 ④その前々月の最終取引価額の月平均額 |
| 投資信託 | 相続発生日の時価 |
| 自社株 | 会社の規模などにより、評価の仕方が異なる |
■相続税申告をする際には、各金融機関で残高証明書を取得
相続発生日の残高を金融機関が証明する書類(証明書の取得には費用がかかる)
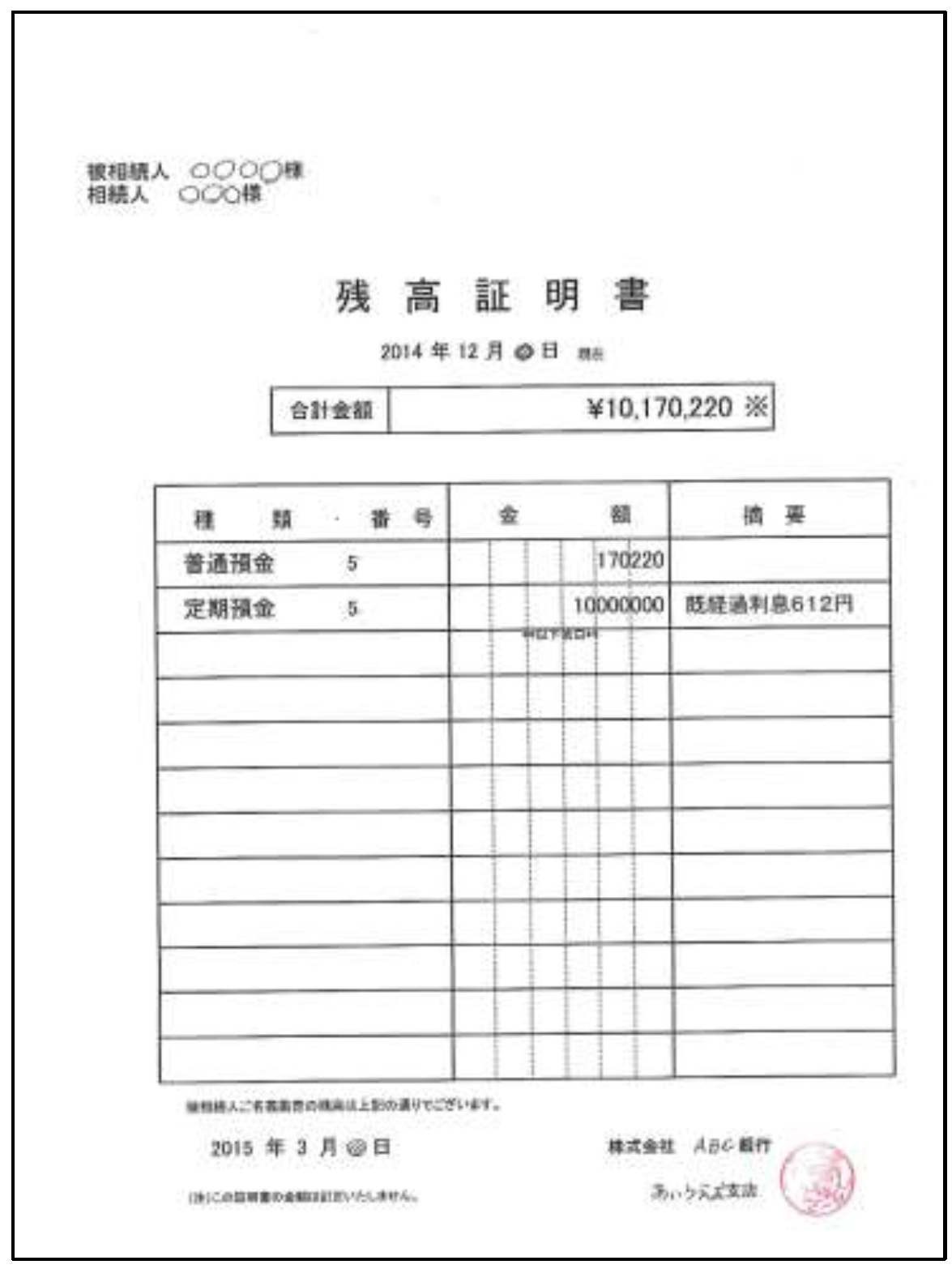
2.不動産の評価
| 建物 | 固定資産税の評価額
|
| 土地 | ①路線価方式(市街地の土地)
②倍率方式(市街化調整区域、農地・山林など)
|
3.金融資産・不動産以外の財産の評価
| 車 | 中古車市場での流通価格 |
| 会員権 | 相続発生時の取引相場を確認し、取引価格の70% |
| 書画・骨董 | 相続発生時における時価
税務署には美術商による鑑定評価書を提出 |
| 家財道具 | 生活規模により、概ね10万~30万円程度で計上 |
| 電話加入権 | 1,500円で計上 |
次回は少し難しいお話しになりますが、不動産の評価方法をもう少し詳しくご説明します。